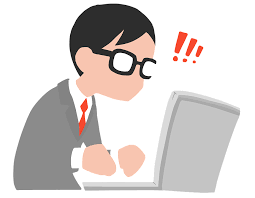みなさん、こんにちは
安心・安全のための生活情報局
局長のやまさきです。
これまでにも当サイトでお伝えしていますが、2017年度税制改正で配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われています。
2018年1月から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額などが大きく改正されています。
これまで夫は妻を税法上の扶養とするために、パート等で妻が働く場合でも年収103万円を超えないようにしていた方が多かったのではないでしょうか。
この世帯で工夫される調整は、いわゆる「103万円の壁」があったからなのですが、この壁が今回の改正で「150万円」まで引き上げられたことはお伝えしてきている通りです。
今回の記事ではもうすぐ年末調整の始まる時期ですので、忘れてしまっている落とし穴にハマってしまわないようにお届けします。
配偶者控除の落とし穴にハマらないために
みなさんは、「103万円の壁」が単純に「150万円の壁」になっただけなので、単純に「47万円分多く働いても扶養に入ったままで家計を助けられる。」なんて勘違いが多いかも知れません。
この考え方は、実は間違った解釈になってしまいます。
今後も配偶者控除を受けるための注意点をお伝えします。
これまでの制度の復習
これまでの制度ではパートタイマーなどで、妻または夫が働くとき(この記事ではわかりやすく説明するために、パートで働く人を「妻」とし、その配偶者を「夫」として表現させていただきます)、2017年までの制度では年収103万円以下の場合、夫は配偶者控除として一律38万円の所得控除を受けることができていました。
この控除は、夫の所得税を低くする効果があり、夫がいくら稼いでいても関係なく、妻の収入をきっちりコントロールすることができれば、配偶者控除が受けられたのです。
また、妻の年収が103万円を超えても、夫は配偶者特別控除を受けることができ、妻の年収が141万円になるまで段階的に減少する仕組みになっていました。
この制度が、2018年1月1日以降、改正され、そのポイントはこの4つです。
改正ポイント
夫の年収が1220万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなくなった
配偶者控除の控除額が一律38万円ではなくなった
妻の年収が201万5999円になるまで配偶者特別控除が受けられるようになった
配偶者特別控除の控除額が夫の合計年間所得によって変わった
このように大きな改正があり、そのポイントは上の4つですが、内容についてはこんな感じです。
夫の年収が1120万円以下で妻の年収が150万円以下であれば、これまでどおり38万円の控除を受けられます。
この点が「150万円までなら扶養枠で働ける」と注目されるようになったのと同時に「150万円まで大丈夫」だけが独り歩きをしてしまい、様々な勘違いが生じ、落とし穴が生まれてしまう原因になりました。
そして、この制度改正で最も大きい影響を受けるのが、年収1220万円超の人たちです。この年収の方々の場合は妻の年収にかかわらず、控除を受けることができなくなっています。
これは、意外と盲点になってしまっているんです。
特に夫の年収が1220万円を超えることが年初から明らかな場合でも、昨年と同様に「103万円の壁」を意識して妻の勤務時間を調整しているケースは多いのではないでしょうか。
「130万円の壁(106万円の壁)」にも注意

ここまでこの記事だけを読んでいただいた方は、夫の年収が1120万円以下であれば、妻は年収150万円まで働いて、配偶者特別控除38万円はこれまでどおりに受けられる。
ということは150万円まで目いっぱい妻に働いてもらえば、「世帯年収が最大限上げることができる!」と考えてしまわれるかもしれませんが、ここに落とし穴があるんです。
その落とし穴の元凶が、社会保険なんです。
社会保険には106万円、130万円の壁があります。
以下の条件に該当すると、いわゆる106万円の壁と言われるものが発生し、短時間で働く場合も妻自身が被保険者として社会保険に加入しなければならなくなってしまうんです。
そうなると、今まで発生しなかった健康保険料や厚生年金保険料が発生し、かえって手取りが低くなってしまうことも考えなくてはなりません。
106万円の壁発生の条件 週の所定労働時間が20時間以上ある 雇用見込が1年以上ある 賃金月額が8万8000円以上ある 学生でない 被保険者数が常時501人以上の企業に勤めている
この106万円の壁に該当しない場合であっても、妻の年間収入が130万円以上になると、妻自身が社会保険に加入することになります。
この壁が存在するためにこの条件に該当しないように働くか、150万円ギリギリまで働くか、フルタイムで突き抜けてしまう働き方もあるでしょう。
ただ、妻が働く職場によっても社会保険に対する考え方が変わってくる点にも注意をしてください。
各会社のルールを理解して世帯年収の最適化を目指しましょう!
最後に注意すべきは会社によっては、妻がいる社員に「家族手当」や「扶養手当」などを支給している場合がるのですが、このときの条件として、妻の収入範囲を要件にしている企業が多く、健康保険の扶養基準や税法上の扶養を基準としている場合が多いんです。
税金の扶養の場合は昨年までであれば、本人(社員)の収入は関係なく、「控除対象配偶者」として妻の年収が103万円あるかどうかで判断していましたが、今年から「源泉控除対象配偶者」となり、本人の年収が1120万円以下で、妻の年収が150万円以下のみが該当することとなってしまっています。
ということは今までと同じようにはいかないということなんです。
会社によって、どこまでを扶養手当の支給範囲としているかは異なりますので、就業規則や賃金規程など、社内のワークルールを改めて確認してください。
税金と社会保険とでは、扶養の範囲が異なっていますし、会社独自に支給している手当を支給している場合は、その基準の考え方も異なります。
これまでにお伝えしてきた改正点を踏まえたうえで、家族にとってベストな働き方を考えて、世帯所得の最適化を考えていただければと幸いです。
参考:配偶者控除の記事一覧
配偶者控除改正!平成30年からの得する共働きの選択と新たな壁
平成30年からの得する共働き家庭を直撃する106万円の壁を解説
パートでの働き方、2018年以降の得な選択は扶養内か扶養外か?
パートで扶養内の人には2018年は決断の年になる!損をしないためには
では、また。